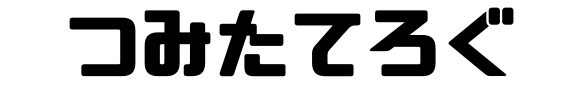この記事ではこんなお悩みを解決できます!
この記事を読むことで、失敗しない新NISAのはじめかたを理解できます。
読み終える頃にはあなたに合った新NISAのはじめかたが知れますよ。
 さのす
さのすFP2級技能士の資格を持つ僕が記事を書きました!
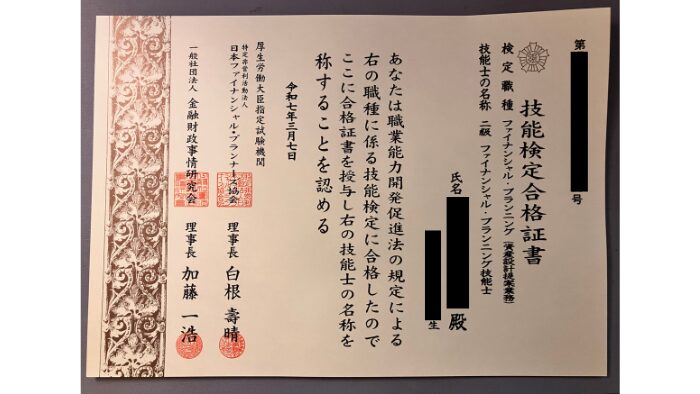
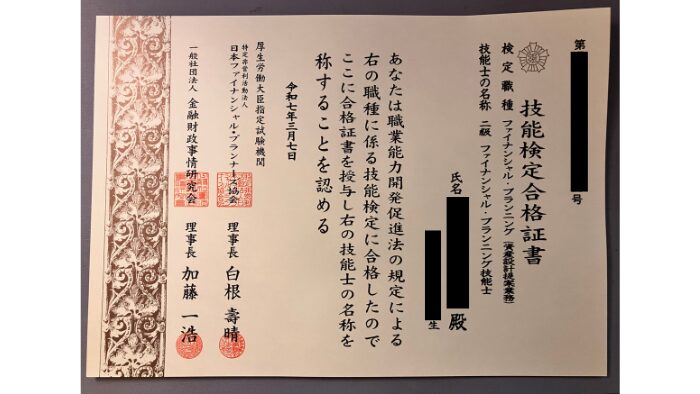
銀行で新NISAをはじめないほうがいい理由
銀行で新NISAを始めるのはおすすめできません。
なぜなら投資の柔軟性やお得さ、選択肢の面でネット証券に比べて不利な点が多いからです。



お得な投資をするために新NISAはネット証券で始めるのがおすすめ。
積立設定に柔軟性がない
銀行では積立設定の変更がしにくく、自由な資金管理が難しくなります。
一度設定した積立額やスケジュールの変更が手間で、柔軟な投資ができません。
| 店舗形態 | 金融機関 | 積立頻度 | 最低積立金額 |
|---|---|---|---|
| 銀行 | 三菱UFJ銀行 | 毎月 | 1000円~ |
| 銀行 | みずほ銀行 | 毎月 | 1000円~ |
| 銀行 | 千葉銀行 | 毎月 | 1000円~ |
| 店舗型証券 | 野村証券 | 毎月 | 1000円~ |
| 店舗型証券 | 大和証券 | 毎日・毎週・毎月 隔月・3ヶ月毎 4ヶ月毎・6ヶ月毎 | 100円~ |
| ネット証券 | SBI証券 | 毎日・毎週・毎月 | 100円~ |
| ネット証券 | 楽天証券 | 毎日・毎月 | 100円~ |
『ボーナス月だけ積立額を増やしたい』
『大きな出費があるから減額したい』
ということがしづらくなります。
柔軟な積立運用をしたいなら、銀行以外の選択肢を検討すべきです。



ネット証券なら積立設定に選択肢が多く、100円から投資できます!
投資信託の運用に限定される
銀行の新NISAでは投資信託しか選べず、投資の自由度が低いです。
個別株式やETFなどの多様な資産に分散投資ができません。
対してネット証券では、高成長が見込める個別株などで大きなリターンを狙えます。



加えてNISAは非課税なので、その恩恵をフル活用できます!
商品選択の幅を求めるなら、銀行での新NISAは適していません。
「いまは積み立て投資枠のみで・・・」
という人でも投資を続けているうちに成長投資枠に投資したくなるかもしれません。
銀行でNISAをはじめてしまうと金融機関ごと変更する手間があります。



気が変わったときのことも考えておきましょう。
クレカ積立・ポイント還元が充実していない
銀行ではクレジットカードによる積立が使えず、ポイントのメリットを享受できません。
ネット証券に比べ、ポイント制度が整っていないからです。
楽天証券なら1%還元で楽天ポイントが貯まります。
対して銀行には、そうした制度がないかごく限定的。
クレカ積立やポイント還元を活用したい人は、銀行以外を選ぶべきです。



クレカ積立なら預金残高を気にすることもありません。
金融商品を勧められる可能性も
銀行では自分に合わない商品を勧められるリスクがあります。
営業ノルマなど、販売側の事情で商品が提案されることがあるためです。
手数料が高い投資信託を「人気です」と勧められ、よく分からず契約してしまうケースも。
自分の意思で投資商品を選びたいなら、営業色の強い銀行は避けた方がよいです。



ネット証券なら自己判断が必要だからこそ、知識が身に付きます!
手数料が高くなる傾向がある
| 手数料 | いつかかる? | 特徴 |
|---|---|---|
| 購入時手数料 | 銘柄購入時 | NISA対象銘柄は無料が多い |
| 信託報酬 | 保有中ずっと | 長期投資では最重要 |
| 信託財産留保額 | 売却時 | ファンド内に残る手数料 |
同じ商品でもネット証券と比べて信託報酬や販売手数料が割高なことが多いです。
信託報酬とは?
口座にお金を預けるときの「口座管理手数料」みたいなもの


投資信託を運用してもらうための「管理費」のこと。
投資信託は専門家(運用会社)が運用してくれます。
しかしそのお礼として、毎日少しずつかかる手数料が信託報酬。
例えば年1%の信託報酬なら、投資した金額の1%が年間手数料として引かれます。



主語は投資を運用する会社です。
運用会社側が手数料として受け取る「報酬」と考えましょう。
信託財産留保額とは?
みんなで出し合った旅行費から、途中で帰る人が少しだけ罰金を払う感じ


投資信託を途中で売るときにかかる「ペナルティ料」のこと。
投資信託は投資家がお金を出し合って運用しています。
したがって途中で抜ける人がいると、他の人に迷惑がかかります。
信託財産留保額とはその分を補うために、売却時に少しだけ引かれるお金のこと。
例えば、信託財産留保額が0.1%なら、10万円分売却するときに100円引かれてしまいます。
ネット証券では販売手数料無料の投資信託が多く、わずかなコストの差が長期的に大きな差を生みます。
コストを抑えて効率よく資産形成したいなら、銀行はおすすめできません。
日本投資者基金の保護を受けられない
証券会社が倒産して投資者の資産が返ってこない場合、最大1,000万円まで補償してくれる公的な保護制度。
株式や投資信託など、預けた資産が証券会社の管理ミスなどで失われたときに備えるもの。
銀行で新NISAをはじめると、日本投資者保護基金の保護を受けられません。
しかし銀行でNISA口座を開設した場合、保護の対象外となります。
例えば新NISAをはじめた銀行が破綻した場合、当然ですが証券会社での保有ではありません。
なので日本投資者保護基金による補償を受けることができないのです。
万が一に備えるならネット証券など、保護対象となる証券会社での口座開設をおすすめします。



証券会社ではじめるだけでリスクヘッジできる!
銀行・対面型証券会社のメリット
銀行や対面型証券会社にも、利用する上でのメリットがあります。
銀行預金との一元管理や住宅ローンの金利優遇など、銀行ならではの特典も存在します。
手続きが簡単
職員のサポートがあるため、書類の記入や提出もスムーズに進みます。
ネットでの申込みに不安がある人でも、店舗で案内を受けながら口座開設できます。
手続きが面倒に感じる人には、銀行・対面型証券会社は安心して利用できるでしょう。
対面でサポートしてくれる
分からないことをその場で質問でき、丁寧な説明を受けられます。
リスクや運用の仕組みについて、専門知識をもった職員が教えてくれますよ。
投資に慣れていない人や不安がある人には、対面サポートは大きな助けになるでしょう。
銀行預金と一緒に管理できる
NISA口座を銀行で持つと、普段の預金口座と一括管理がしやすくなります。
アプリやネットバンキングで資産の全体像を把握しやすくなるためです。
同じアプリ内で残高確認や資産推移が見られるため、家計管理も効率化できるでしょう。



まとめて管理したい人には、銀行のNISA口座が便利。
住宅ローンの金利優遇
銀行によっては、NISA口座を開設することで住宅ローンの金利が優遇される場合があります。
NISA口座の開設を含むいくつかの条件をクリアすることで、住宅ローンの金利優遇を受けられます。
住宅ローンを利用している人は、金利優遇があるか確認しておきましょう。
ただしNISA口座の開設は必須ではなく、金利優遇の条件を満たすための一項目に過ぎません。



銀行でNISA口座を開設するデメリットも考慮すべきです。
NISA口座選びのポイント
NISA口座を選ぶ際は、投資したい銘柄やスタイルに合ったネット証券を選ぶことが失敗しない秘訣。
証券会社によって取扱商品や積立条件、サービス内容が微妙に違ってきます。
したがって自分に合ったネット証券を選ばないと、選択肢が狭まったり無駄な手数料が発生したりします。
以下の3点を確認しましょう。



自分の投資目的に合ったネット証券を選びましょう。
買いたい銘柄があるか
自分が購入したい銘柄を取り扱っている金融機関を選ぶのが肝心。
証券会社によって、取り扱い商品には違いがあります。
個別株や海外ETFを購入したい場合、それに対応しているネット証券を選ぶ必要があります。
最低積立金額
積立を無理なく続けるには、最低積立金額を確認することが重要。
証券会社によっては毎月1,000円から積立できるところもあれば、より高額からのところもあります。
楽天証券では100円から積立が可能ですが、銀行によっては1万円以上必要な場合もあります。
自分の予算に合わせて無理なく積立できるかを確認しましょう。



積立設定の柔軟性も忘れずにチェック!
サービスの充実度
使いやすさやサポート体制など、サービスの充実度も口座選びの重要な要素。
長期にわたる資産運用では、取引ツールやサポート体制の使い勝手が影響するでしょう。
具体例を挙げると、SBI証券と松井証券のサービスが充実しています。
SBI証券は使いやすいアプリと豊富な投資情報で評価されています。
初心者でも安心して利用できるでしょう。
松井証券は対面型の証券から、ネット証券へ完全移行した証券会社として知られています。
ネット証券のなかでは手厚い顧客サポートが特長。



安心して運用を続けるためにも、サービスの質や利便性は事前に確認!
ネット証券がおすすめの人
ネット証券は低コストで自由度の高い投資環境を提供しています。
以下のようなニーズを持つ人にはネット証券の利用が強くおすすめ。



特に自分のペースで運用したい人向き。
コスト安くしたい人
運用コストをとにかくおさえたいならネット証券一択。
ネット証券は購入時手数料や、信託報酬が低い商品が豊富にそろっているためです。
SBI証券や楽天証券ではノーロード(購入手数料無料)の投資信託が多数あります。
特に信託報酬はファンドの保有中ずっとかかるので要確認。



長期投資でコストを抑えたい人は、ネット証券を選びましょう。
自分で管理できる人
自己判断できる・したい人にもネット証券はおすすめ。
自分の判断で商品を選び、好きなタイミングで売買できるからです。
アプリを使ってリアルタイムで状況を確認し、気になる銘柄をすぐに購入可能。



ネット証券は銀行に比べて自由度の高さが魅力です。
クレカ積立をしたい人
クレジットカードで積立投資をしたい人にはネット証券が最適。
多くのネット証券がクレカ積立に対応し、ポイント還元もあるからです。
楽天証券を例に挙げると、楽天カードで積立すると1%の楽天ポイントが還元されます。
クレカ決済で投資効率を高めたい人にはネット証券がお得。



ネット証券であっても、クレカ積立未対応の証券もあるので注意!


おすすめのネット証券
新NISAを始めるにあたって、ネット証券を選ぶことには銀行と比べて多くのメリットがあります。
低コストで多様な商品を取り扱い、ポイント還元やクレカ積立などのサービスが充実しているからです。
とくにおすすめのネット証券をまとめました。



ネット証券でも様々なので違いを要チェックです!
楽天証券
- 各種手数料が無料
- ポイント投資ができる
- キャッシュレスで月15万円まで積立可能
| 取扱銘柄数(投資信託) | 1,138銘柄 |
|---|---|
| 取扱銘柄数(米国株) | 4,698銘柄 |
| 取扱銘柄数(単元未満株) | 1,575銘柄 |
| クレカ積立(ポイント付与率) | 楽天カード(0.5%〜1.0%) |
| ポイントサービス | 楽天ポイント楽天証券ポイント |
| ポイント投資 | 投資信託日本株単元未満株米国株 |
マネックス証券
- 年会費無料カードの中で最高のクレカ積立還元率
- 銘柄スカウターが便利
- 中国株の売買手数料が実質無料
| 取扱銘柄数(投資信託) | 1,124銘柄 |
|---|---|
| 取扱銘柄数(米国株) | 4,968銘柄 |
| 取扱銘柄数(単元未満株) | 3,900銘柄以上 |
| クレカ積立(ポイント付与率) | マネックスカード(0.2%〜1.1%) dカード |
| ポイントサービス | マネックスポイント dポイント |
| ポイント投資 | 投資信託(積立を除く) |
SBI証券
- 手数料が無料
- ポイントやクレカ積立のサービスも充実
- 取扱銘柄数・商品数が多い
| 取扱銘柄数(投資信託) | 1,181銘柄 |
|---|---|
| 取扱銘柄数(米国株) | 5,205銘柄 |
| 取扱銘柄数(単元未満株) | 3,900銘柄以上 |
| クレカ積立(ポイント付与率) | 三井住友カード(0.5%〜5.0%) |
| ポイントサービス | Vポイント(Tポイント)Pontaポイント dポイント JALのマイル PayPayポイント |
| ポイント投資 | 投資信託日本株単元未満株 |
松井証券
- 日本株や米国株の投資相談ができる
- 投信残高ポイントの還元率が業界最高水準
| 取扱銘柄数(投資信託) | 1,078銘柄 |
|---|---|
| 取扱銘柄数(米国株) | 3,804銘柄 |
| 取扱銘柄数(単元未満株) | 売却のみ |
| クレカ積立(ポイント付与率) | 非対応 |
| ポイントサービス | 松井証券ポイント |
| ポイント投資 | 投資信託(3銘柄) |
まとめ
銀行で新NISAをはじめないほうがいい理由
新NISAを始める際、対面サポートの安心感を得るなら銀行・対面型証券会社も選択肢に入ります。
しかしながら初心者であっても、
- 「低コスト」
- 「柔軟性」
- 「商品選択の幅」
などを重視するならネット証券が最適。
手厚いサポートよりも、自分で学びながら着実に資産形成をしていきたい方には、ネット証券が断然おすすめです。



初心者でも自由度とコスト重視ならネット証券が有利!